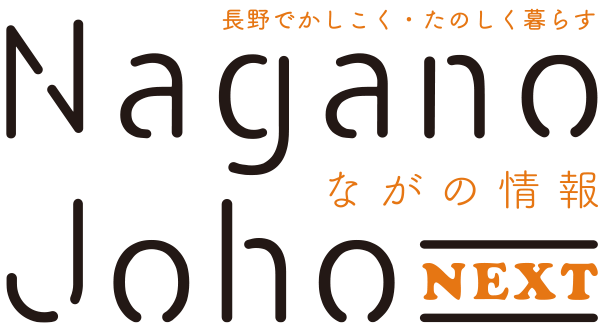-

金融リテラシー教育を通して
地域社会に貢献し
信頼される金融機関として
日々の暮らしを守っていく。-
長野信用金庫
(右から)
近藤 佑樹さん
下平 満範さん
前嶋 光さん
田島 祥子さん
-
長野信用金庫
-

2015年の国連サミットで「SDGs」が採択され、2030年までに達成すべき世界共通の目標が示されてから、今年で10年。私たちは、持続可能な社会へと舵を切れているのでしょうか。
このシリーズでは、さまざまな課題解決のために、長野の企業や団体がどんな取り組みを始めているのかをご紹介します。今回は、長野信用金庫の各職場より、下平満範さん、前嶋光さん、近藤佑樹さん、田島祥子さんにお話を伺いました。
地域の皆さまとともに
100年、歩み続けて。
 長野信用金庫は、大正12(1923)年より業務を開始し、令和5(2023)年に創立100周年を迎えました。北信地区の皆さまとともに100年歩んでこられたことに感謝すると同時に、次の100年のために自分たちができること、やるべきことは何かを改めて自らに問い、行動し始めています。
長野信用金庫は、大正12(1923)年より業務を開始し、令和5(2023)年に創立100周年を迎えました。北信地区の皆さまとともに100年歩んでこられたことに感謝すると同時に、次の100年のために自分たちができること、やるべきことは何かを改めて自らに問い、行動し始めています。
そのひとつが、高校生や短大生、大学生に向けた金融リテラシー教育です。成人が18歳になった今、金融に関する正しい知識を持たないまま大人になる若者たちの周囲には、さまざまな課題やトラブルが発生しています。こうした問題を回避し、自分の暮らしを守るために正しい知識を得ることは、非常に重要なことだと考えています。難解に思われる金融の情報を、実生活に即した内容でわかりやすく伝えること、いずれ社会に出る若者に「働いて稼ぐ」ことの意味や、「将来設計」の必要性を自ら考えてもらうことが、私たちの目指す金融リテラシー教育です。
正しい知識によって健全な経済生活を送る人を増やすことで、地域全体の健全な経済循環につなげていく。北信地区全体の活性化のためにも、長野信用金庫では金融リテラシー教育を、成すべき地域貢献の大きな柱と位置づけ、独自の「金融リテラシー講座」プログラムを開発。現在は、主に長野工業高等学校の2学年に対し、教育の実践を始めています。
人と地域をつなぐことで
地域全体を元気に。
 「金融リテラシー講座」は、いくつかのステップで構成されています。はじめに、毎年5月に開催される「長野しんきんビジネスフェア」を見学し、地域を支えるさまざまな企業の事業内容を知ることで、「働く」ということへの意識、関心を高めます。第1回、第2回の講座では、お金の貯め方や投資の基本、お金を借りるということや契約の基本などを座学で学び、第3回では、地域の企業の方にご登壇いただいて、「働いて稼ぐ」ということを、より身近なこととして捉えられるよう講義をお願いしています。長野工業高校は分野別に6つの科に分かれているので、それぞれの科ごとに興味のある企業に依頼。自分たちが目指す分野の企業の講義は高校生にも好評で、これをきっかけに、その企業に就職した生徒さんたちもいます。
「金融リテラシー講座」は、いくつかのステップで構成されています。はじめに、毎年5月に開催される「長野しんきんビジネスフェア」を見学し、地域を支えるさまざまな企業の事業内容を知ることで、「働く」ということへの意識、関心を高めます。第1回、第2回の講座では、お金の貯め方や投資の基本、お金を借りるということや契約の基本などを座学で学び、第3回では、地域の企業の方にご登壇いただいて、「働いて稼ぐ」ということを、より身近なこととして捉えられるよう講義をお願いしています。長野工業高校は分野別に6つの科に分かれているので、それぞれの科ごとに興味のある企業に依頼。自分たちが目指す分野の企業の講義は高校生にも好評で、これをきっかけに、その企業に就職した生徒さんたちもいます。
第4回では信金職員がファシリテーターとなり、学んだことをワークショップ形式でまとめ、グループごとにレポートを作成します。もっとも優秀なグループは「長野しんきんビジネスフェア」のメインステージで成果発表を行い、それを次年度、金融リテラシー講座を受講する生徒さんが見学。先輩たちのプレゼンテーションを聞くことから、次の「金融リテラシー講座」が始まっていくのです。
年間を通して行われる「金融リテラシー講座」は、学校側から「ぜひ継続してほしい」と好評で、また、登壇をお願いする企業の皆さまからも「高校生に自社の業務内容や社風を知ってもらう良いきっかけになった」と高評価をいただいています。各プログラムは、総合企画部や地域みらい応援部、業務推進部のマネーアテンダントや各支店の営業担当など、部や支店を横断して実施しており、より興味を持ってもらえる内容や伝え方を検討しながら、毎年少しずつブラッシュアップしています。これからも私たちができる地域貢献の在り方を模索しながら、さまざまな取り組みを推し進めていきたいと思います。